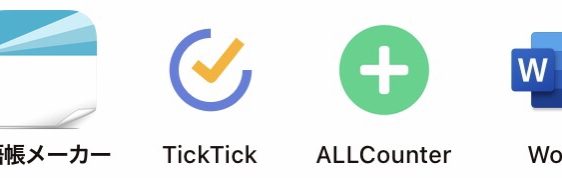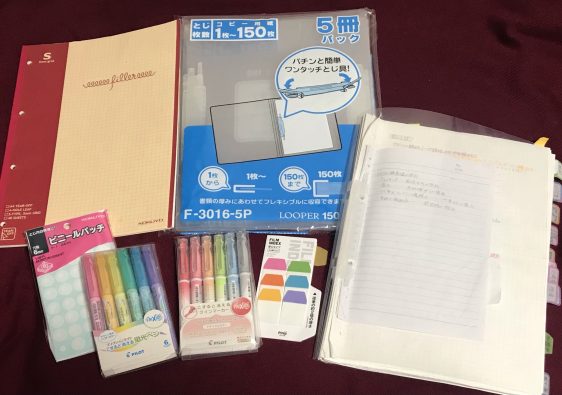おかげさまで先日、無事第67回臨床検査技師国家試験の合格が決まりました。
合格までに私がしたこと・模試の成績などを公開します。
何かの参考になりましたら幸いです。
私の通っていた学校は臨床検査技師だけの専門ではなかったので(こう言うとわかる方にはわかってしまうかもしれませんが…)、他の分野をメインとして勉強しながら臨検資格取得のための勉強をしていました。
もくじ
大学入学から試験当日までの体験記
1・2年生〜
臨検にはほとんど関わらず過ごしていました。強いて言えば基礎となる生理学や生化学といった科目は、資格以外の科目と同じように講義・実習を受けていました。
勉強以外では、運動部とゆるめの文化部の部活を二つかけもちしながら、週2でアルバイトもしていました。
3年生〜4年生前期
講義・実習は臨床検査技師の専門科目がメインになりました。実習、卒業研究、就活を並行して行うため、この時期が一番大変でした。正直臨検の勉強に手を回す余裕はまだありませんでした…。
3年半ばあたりから、スケジュールが不規則になったことと、時間を確保したいという考えから、アルバイトは単発や在宅でできるものに切り替えました。これは受験の一ヶ月前くらいまで続けていました。
4年生夏 病院実習
この時期に、一ヶ月間の病院での現地実習がありました。ここで現物や現場を見ることで、身についた知識や、これから学ぶ上でイメージができるようになり、導入となった知識もとても多いです。
特に一般検査・輸血・病理は実際の工程を目で見てみることで覚えられた部分が多いです。
実習は基本的に平日朝から夕方まであり、課題も出るため、実習と別で勉強時間を取るのは難しいと感じました。
4年生9月〜 受験勉強開始!
9月末から模試が始まりました。
受験までの間、模試10回程度(とその復習)、金原の問題集演習 一周弱 を行いました。
勉強内容については、こちらの記事に書いています。→http://rinken.ltt.jp/2021/03/02/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%be%8b%ef%bc%88%e7%a7%81%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88%ef%bc%89/
また、成績の推移は後に記します。
勉強時間としては、9・10月は週の半分程度の日に、11月・12月は平日に5時間程度、1月からは毎日、3時間〜10時間ほど勉強していました。
試験一ヶ月前に中だるみで勉強が思うように進まなかった時期もあります。その時は週に1日何もしないなど、休む日を設けて無理なく続けました。
4年生 2月 いざ本番
日が迫ってきても、もう本番なのだろうか?とあまり実感がありませんでした。前日は友人と会場近くのホテルに泊まり、その日は6時間ほど勉強していたと思います。
追い込みとして不安のあるところを口頭で教えあえて、なおかつ同じ状況の相手と一緒の安心感もあり、話せて息抜きにもなり、個人的には良かったです。この時友人と話していた問題が本番にも2問出ました。笑
本番当日ですが、試験形式が医歯薬の模試とそっくりなので、あまり緊張せずに受けることができました。
なお、試験に使うもの以外をしまう指示があってから説明時間が30分程度とられており、待ち時間は長く感じました。直前に暗記してすぐに書き写す方法をとろうと思っている人は注意が必要だと思います。
試験中は申告した上でのトイレ退室や、解き終わった人の途中退室が可能であるため(タイミングは決まっていますが)、退室できない空間が苦手な方も受けやすい環境かなと思います。
試験時間自体は、個人差があるとは思いますが、丁寧に解いた後見直しを2周してちょうど良いくらいの時間に感じました。
試験の問題は後日公開されると思うので詳細は省きますが、少し傾向が変わっていることや、得意分野でも解けない場合があることを感じました。
特に今年は写真問題でマラリアが出ましたが、例年のものとは写り方がかなり違いました。山を張りすぎないで、何かがだめでも他で点数をカバーできるようにしておく必要があると思います。
単純ではない問題も多く、体感ではとれたのは120点ぎりぎりくらいかな…?といったところ。不安もありましたが、帰って自己採点すると150点に届いていました。友人も同じようなことを言っていたので、体感より取れている可能性はあるかと思います。
自己採点に関しては、教育機関や出版社などから模範解答の速報を用いている人が多いようですね。
本番までの成績の推移
9月末模試(医歯薬) 82点 11月模試(医歯薬) 80点 12月模試 130点 1月模試 2月模試 145点 本番 150点(解答速報による自己採点 成績が開示されたら公式なものも書きます)
私の場合、半年前は合格点に全然届いていませんでしたが、11月頃金原の問題集を解くようになってから点が伸び始めました。(それまでは模試の復習が中心でしたが、あまり伸びなかったように思います。
国試の勉強は範囲が広く忘れやすいため、点数が伸びにくいとも聞きます。しかし、問題が選択形式であることや、頻出分野が決まっていることから、初見の分野をなくすほど点数は上がると感じました。
周りの話を聞く限り、少なくとも7割程度まではそれが可能ではないかなと思います。
さて、ここまで読んで頂いて感じた方も多いと思いますが、受験勉強期間は短い方だと思います。また、学校の仕組み上、実習期間も一般的な臨床検査技師養成過程よりおそらく短いです。でも、意外となんとかなります。
(より時間があれば、さらに自信を持って受験ができるので、なるべく早く始めるにこしたことはないと思いますが、様々な事情で難しい人もいると思います。)
ですので、半年前だけど勉強が追いついていない、成績が伸びないなどで悩んでいる方も不安がらずに構えて大丈夫だと思っています。
私の場合、効率よく勉強できたのは先生方のご指導と、講義を受けている際・テスト勉強の際に作っていたまとめノートによるところが大きいです。先生方には本当に感謝するばかりです。
ノートは作っている方はぜひ活用してみてください!
なお、つくっていない方でも短時間で勉強する際に助けになるよう、このブログでもノートを公開していきます。個人的なものではありますが、よければご利用ください。他にもまとめをあげてくださっている方はいますので、探してみるのも良いと思います。
Q&A
最後に、これまでにご質問頂いたことや、私が臨検の受験をする際に疑問に思っていたことなどを記していきます。他にご質問などありましたら、コメント欄でぜひお聞かせください。
Q. 臨検の教科の成績は、他教科の成績と関連するか
A. いいえ だと思います。出題分野や問題の型などの特性上、高校までや大学での一般的な勉強ができる/できない からといって、国試でもそうとは限りません。
私は学校の成績は悪い方ではありませんでしたが、暗記が苦手だったので、筆記がなく、また土台となる新しい知識が幅広く必要になる臨検の勉強は苦戦しました。学校で単位取得のための再試や課題をしたこともしばしば…。
暗記や計画を立てて実行するのが得意な人は伸びやすいかなと思いました。
Q.臨検受験を目指すにあたり、事前に学習しておいた方がいいことはあるか
A.高校で生物・化学・物理は学んでおいた方がいいと思います。
生物・化学・また、中学で習う実験器具の使い方などは、基礎の基礎がそのまま出題されていました(細胞分裂や濃度の計算など)。つまりしっかりやっておけば、これまでの知識だけで解けるものが多いです。
また、医用電子工学は高校物理が土台になっています。私は生物・化学選択で物理を基礎しかやっていなかったので、初めて講義を聞いた時は何を言ってるのかすらわかりませんでした。これは高校物理がわかれば解決すると思います。
Q. 息抜きはしていたか
A. していました。国試二週間前くらいまでは友人と通話をしたり、漫画を読んだりしていました。午前中は休もう!と1日に10冊読んだりしていましたが、そのぶんリフレッシュができ、だらだら続けるよりもその後充実した勉強ができたと思います。
勉強で疲れてくると色々おっくうになるので、頭・体力を使わない趣味を重宝しました。